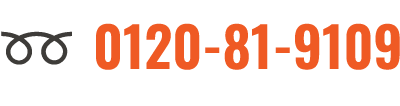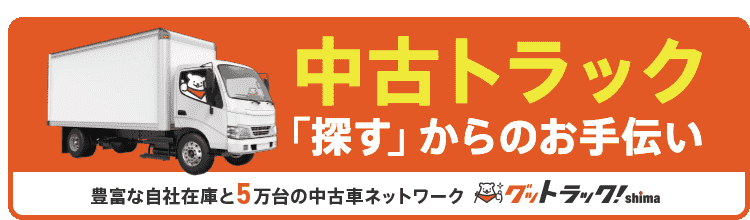2023.09.07
普通免許で乗れるトラックは何トンまで?中型・大型免許を取得する方法も紹介
こんにちは!グットラックshimaです!
普通免許でも運転できるトラックはありますが、何トンまでが可能なのかご存じでしょうか?
実は、取得した年によっては普通免許で運転可能なトラックは異なるんです。
もちろん10トン級の大型トラックでも大丈夫という訳ではなく、普通免許で運転できるトラックの大きさには制限があります。
今回は、普通免許では何トンのトラックまで運転できるのかを解説します。
また、普通免許では運転できない車両を運転するにはどんな免許が必要なのでしょうか。
中型免許・大型免許を取得するための条件も、あわせてご紹介します。
中古トラック一覧
目次
普通免許で乗れるトラックは何トンまで?
普通免許で乗れるトラックが何トンかは、すぐに「ズバリ何トンです!」とは言い切れません。
まずは、お持ちの普通免許がいつ取得したものかを確認する必要があります。
道路交通法の改正により、普通免許を取得した年によって乗れる車両が変わってくるからです。
では、普通免許を取得した年別に見ていきましょう。
お持ちの免許証で取得年月日をご確認くださいね。
平成19年6月1日までに取得した普通免許の場合
車両総重量は8トン未満、最大積載量は5トン未満、乗車定員は10人以下のトラックを運転可能です。
平成19(2007)年6月1日までは中型免許が存在しなかったため、日本で一番使われているトラックのサイズである中型の「4トントラック」を、普通免許で運転することができます。
平成19年6月2日〜29年3月11日に取得した普通免許の場合
車両総重量は5トン未満、最大積載量は3トン未満、乗車定員は10人以下のトラックを運転可能です。
この期間に普通免許を取得した方は、いわゆる「2トントラック」といわれる準中型トラックまで運転可能です。
平成29年3月12日以降に取得した普通免許の場合
車両総重量は3.5トン未満、最大積載量は2トン未満、乗車定員は10人以下のトラックを運転可能です。
平成29年3月12日に改正法が施行、準中型免許が新設されたため、準中型免許の範囲が普通免許から外されました。
小型サイズの「1トントラック」「軽トラック」が運転できます。
普通免許で運転できないトラックとは?必要な免許を紹介
トラックを運転するための免許には、普通免許以外に、準中型免許・中型免許・大型免許の3種類があります。
ここでは、普通免許では運転できないトラックの種類について、それぞれの免許がどんな運転区分なのか、具体的に何トンまでなら運転できるのかを確認していきましょう。
準中型免許で運転できるトラック
運転可能なトラックは、車両総重量は3.5〜7.5トン未満、最大積載量は2〜4.5トン未満、乗車定員は10人以下のものです。
企業間や工場など、また中小企業の運送でも多く使われているサイズです。
保冷車や冷凍車などもこのサイズが多く、物流を下支えしている免許といえます。
中型免許で運転できるトラック
運転可能なトラックは、車両総重量は7.5〜11トン未満、最大積載量は4.5〜6.5トン未満、乗車定員は11〜29人以下のものです。
4トントラックはもちろん、小型バスや6トントラックまで運転できます。
身近なところでは、ホームセンターなど、大きな商品を扱う店舗配送に欠かせません。
ちなみに中型トラックは最大積載量を上げる「増トン」という方法も可能です。
ただし、最大積載量が6.5トンtを越えると大型免許が必要になるので、ご注意くださいね。
増トンに関してはこちらのコラムも参考にどうぞ!
トラックの増トン車とは?増トン車のメリットや必要な免許を解説!
大型免許で運転できるトラック
運転可能なトラックは、車両総重量は11トン以上、最大積載量は6.5トン以上、乗車定員は30人以上のものです。
物流の花形、大型トラックが運転できる大型車両のエキスパートです。
ミキサー車やダンプカー、大型バスなどの大型車を運転することができます。
普通免許以外のトラックの運転免許を取得するには?

普通免許では運転できないトラックを運転するには、準中型免許・中型免許・大型免許を取得しなければなりません。
「種類も多いし簡単には取れないのでは?」
「高い費用もかかりそう…」と不安に思っていませんか?
ここでは、準中型免許・中型免許・大型免許をどうすれば取得できるのか、またどれくらいの費用がかかるのか、そして合格率までをご紹介します。
普通免許だけでは得られないメリットもありますよ!
準中型・中型・大型免許はどこで取れる?
普通免許と同じように、自動車教習所を利用するのが一般的です。
なかには教習を受けず一発試験に挑む猛者もいますが、普通免許以上に難易度の高い試験になっています。
普通免許と変わらず通学の教習所や合宿の教習所が選べますので、ライフスタイルに合った教習所を探してみてくださいね。
準中型・中型・大型免許を取る条件は?
準中型免許は18歳から取得可能なため、18歳になったらすぐに普通免許の教習にプラスして取ることができます。
中型免許は20歳以上、かつ普通免許を取得してから2年以上経過して大型免許になると21歳以上かつ普通免許・中型免許・大型特殊免許のいずれかを取得してから3年以上が経ってからという条件でしたが、実は2022年5月に改訂がされています。
中型・大型免許ともに、19歳以上で普通免許を1年以上保持していることが条件になり、少し規制が緩みました。
しかし、19歳以上で取る場合は普通免許等取得後に受験資格特例教習を受ける必要があります。
また、受験資格特例教習を受けて免許を取得したあとは、本来の免許取得年齢(大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達する日まで、「若年運転者期間」とされることも覚えておきましょう。
準中型・中型・大型免許を取得する費用は?
準中型免許は普通免許と一緒に取得可能なため、一気に取る場合はトータルで30〜40万円程度。
普通免許を取得し終えてから別途準中型免許のみ取得する場合は、12〜18万円の費用がかかります。
中型免許と大型免許は普通免許と同時に取得できず、中型免許のみで10万円台から高くて30万円程度、大型免許のみでは20〜40万円程度を用意する必要があります。
もともと持っている免許がAT限定かどうか、また繁忙期か否かなどで取得費用がかなり異なってくるので、教習所はいくつか比べてみるのがベストです。
普通免許以外の合格率は?
警視庁の運転免許統計によれば、令和4年中の合格率は準中型免許が90.4%と、難易度の高い免許ではないことがわかります。
これに対して中型免許は一種免許が99.2%、お客さんを乗せて走ることのできる二種免許が79.3%です。
大型免許になると一種免許は95.0%ですが、二種免許は63.6%とかなりの難関になってきます。
普通免許以外の免許を取るメリットは?
なんといっても就くことのできる職種が広がるのがメリットです。
中型免許や準中型免許などの比較的新しい免許区分は、運送・物流業界の人手不足を解消するのに設けられた側面もあります。
資格手当や特別手当など待遇面でも優遇されることがあり、収入アップが期待できるのも嬉しいポイントですよね。
中古トラック一覧
近年の普通免許で乗れるのは「1トントラック」「軽トラック」!
普通免許について、取得年月日で何トンのトラックに乗れるかが違ってくる制度はちょっと複雑ですよね。
平成19年6月1日までに取得した普通免許の場合は車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員は10人以下。
平成19年6月2日〜29年3月11日に取得した普通免許の場合は、車両総重量は5トン未満、最大積載量は3トン未満、乗車定員は10人以下で、平成29年3月12日以降に取得した普通免許の場合は、車両総重量は3.5トン未満、最大積載量は2トン未満、乗車定員は10人以下のトラックを運転可能です。
共通しているのは、どの年代の普通免許でも「1トントラック」「軽トラック」の運転は可能ということ。
取得年月日によっては、普通免許でも4トントラックが運転できます。
間違えて自分が運転できないトラックを購入したりしてしまうことのないように、今一度お手元の免許証で取得年月日を確認してみてくださいね。
トラックの購入、買取のご用命はグットラックshimaまで、お問い合わせお待ちしております!


 企業情報
企業情報