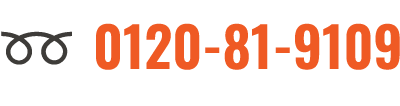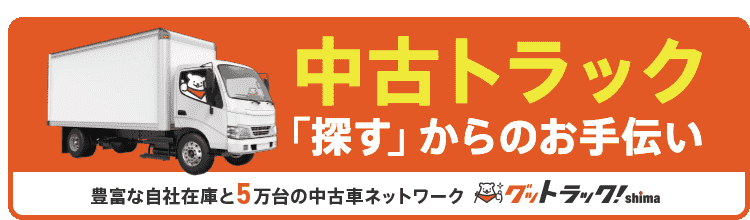2023.09.10
トラックの高速料金は車種区分で決まる!見分け方も解説
こんにちは!グットラックshimaです!
トラックで荷物を配送する際に、高速道路を利用する人は多いのではないでしょうか。
高速道路を利用すると、一般道よりもスムーズに時間をかけずに配送先へ荷物を運べます。
しかし、高速道路を使うには料金を支払う必要がありますが、高速料金はどのように決まるのかわからない人もいるでしょう。
結論として、高速道路の料金は車種区分と走行距離によって決まります。
今回は、トラックの高速料金の決まり方や高速道路における車種区分についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
中古トラック一覧
目次
トラックの高速料金は車両区分や走行距離で決まる!
先述した通り、トラックの高速料金は車種区分と走行距離が関係しています。
また、走行距離や時間帯による割引もあるため、その兼ね合いにより料金が決定します。
詳しく説明していきましょう。
車種区分による高速料金の違いとは
車種区分とは、自動車の種類を分けるために用いられているものです。
自動車の形状や用途、大きさなどによって分けられます。
高速道路だけでなく、道路交通法や道路運送車両法などの法律によって区分の内容は異なります。
高速道路における車種区分は以下の通りです。
- 軽自動車等:軽トラックや軽バンなどの軽貨物
- 普通車:2tトラックなどの小型貨物自動車
- 中型車:3〜4tトラックなどの普通貨物自動車
- 大型車:最大積載量5t以上のトラックなど
- 特大車:4車軸以上のトラックや大型特殊自動車など
トラックに関する車両区分について、さらに詳しくお伝えすると以下の通りです。
普通車
- 二輪自動車および側車付二輪自動車を除く小型自動車
- 普通乗用自動車
- けん引軽自動車と被けん引自動車1車軸との連結トレーラー
中型車
- 普通貨物自動車(車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満で3車軸以下の普通貨物自動車、被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタで2車軸の普通貨物自動車
- けん引軽自動車と被けん引自動車2車軸以上との連結トレーラー
- けん引普通車と被けん引自動車1車軸との連結トレーラー
大型車
- 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で3車軸以下、および車両総重量25t以下(最遠軸距5.5m未満または車長9m未満のものについては20t以下、最遠軸距5.5m以上7m未満で車長が9m以上のものおよび最遠軸距が7m以上で車長9m以上11m未満のものについては22t以下)かつ4車軸の普通貨物自動車、けん引普通車と被けん引自動車2車軸以上との連結トレーラー
- けん引中型車と被けん引自動車1車軸との連結トレーラー
- けん引大型車2車軸と被けん引自動車1車軸との連結トレーラー
特大車
- けん引中型車と被けん引自動車2車軸以上との連結トレーラー
- けん引大型車と被けん引自動車との連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のトレーラー
- および特大車がけん引する連結トレーラー、大型特殊自動車
ただし、それぞれの車種の車軸間距離が1m未満の場合、複数の車軸数であっても料金車種区分の判別において1車軸として扱われます。
被けん引自動車の車軸間距離が1m未満の場合、ETCの無線走行はできない決まりとなっているため注意が必要です。
また、車種区分による高速料金の違いも、東北自動車道の「仙台宮城IC〜宇都宮IC」を走行した際を例にしてご紹介します。
| 車種区分 | 通常料金 | ETC料金 | ETC2.0料金 |
| 普通車 | 5,460円 | 3,820円 | 3,820円 |
| 中型車 | 6,520円 | 4,560円 | 4,560円 |
| 大型車 | 8,900円 | 6,230円 | 6,230円 |
| 特大車 | 14,700円 | 10,290円 | 10,290円 |
※平日午前0時からの利用、移動距離229.4kmの想定
トラックのサイズが大きくなるにつれて高速料金も上がるため、維持費などのコストにも注意が必要です。
「燃費向上!トラックの省エネ運転のコツと事例を解説」では、トラックの燃費をアップさせる方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
仮ナンバーの車種区分についてもチェック
仮ナンバーとは、以下の番号標を総称したものです。
- 試運転や検査を受けるための回送、またはその他の特別な理由がある場合に使われる「臨時運行許可番号標」
- 自動車の製作や陸送、販売業車が回送運転する場合に用いる「回送運行許可番号標および臨時運転番号標」
仮ナンバーのトラックの場合、車軸数が2つの場合は普通車となり、軽自動車規格の場合は軽自動車等に区分されます。
そのほか軸数が3つの場合は中型車、4つの場合は大型車として分けられ、現在ではあまり見られませんが、車軸数が5つの車両は特大車として扱われます。
走行距離や時間帯でも高速料金は変わる
高速道路は走行距離が長くなるほど料金が高くなります。
高速道路の料金には、走行距離が長くなるほどに料金の割引率が上がる「長距離逓減制(えんきょりていげんせい)」が設けられており、現在は100〜200kmで25%、200km以上で一律30%の割引が適用されています。
現行の割引率に加えて、新しく適用される予定の割引率は以下の通りです。
| 走行距離 | 割引率 |
| 400〜600km | 40% |
| 600〜800km | 45% |
| 800km以上 | 50% |
現行制度よりも割引率の範囲が広がるほか、1,000km以上走行した場合には5年間の「激変緩和措置」も適用されるため、長距離を走るドライバーにとってはメリットとなるでしょう。
一方、深夜割引は、対象となる高速道路を、ETCを利用して0時から4時までの間に走行していれば、通行料金が30%割引になるというもの。
現在深夜割引についても見直しが検討されています。
トラックの車種区分の見分け方も確認!
トラックの車種区分は以下の3つによって見分けられます。
- 車体の寸法
- ナンバープレートの大きさ
- 分類番号
所有しているトラックがどの車種区分に該当するのか見分けられるよう、参考にしてください。
車体の寸法
車体の寸法で見分ける場合、車両総重量や最大積載量、トラックが何tトラックなのかを確認しましょう。
例えば、以下のような見分け方になります。
- 最大積載量 3.0t以内/車両総重量 5.0t以内:2t・3tトラックと呼ばれる小型トラック
- 最大積載量 6.5t以内/車両総重量 11t以内:4tトラックと呼ばれる中型トラック
- 最大積載量 6.5t以上/車両総重量 11t以内:10tトラックと呼ばれる大型トラック
ナンバープレートの大きさ
ナンバープレートの大きさによってもトラックの車種区分が見分けられます。
小型トラックと中型トラックは「縦16.5cm横33cm」の中型標板、大型トラックは「縦22cm横44cm」の大型標板が使われます。
分類番号
ナンバープレートの地名の横に記載されている番号の桁が大きい部分が「分類番号」です。
ナンバープレート上部の番号は1桁から3桁の番号が記載されており、トラックの種類によって番号が振り分けられています。
トラックの場合、1ナンバーと4ナンバーなので分類番号は1または4となります。
トラックの分類番号の詳細は以下の通りです。
| 1ナンバーのトラック(中型車・大型車・特大車) | 1、10〜19、100〜199 |
| 4ナンバーのトラック(小型トラック) | 4、6、40〜49、60〜69、400〜499、600〜699 |
次に1ナンバーと4ナンバーの登録条件についてご紹介します。
1ナンバーの登録条件は以下の通りです。
- 「長さ4.7m、幅1.7m、高さ2m、排気量2,000cc」を超えていること
- 荷台の面積が1㎡以上あること
- 座席部分よりも荷台スペースが広いこと
- 荷台に積載した荷物の重量が乗車した人員よりも重いこと
- 座席と荷台の間に仕切りが設けられていること
- 人が乗車する場所と荷台の間に人が移動できないような構造となっていること
4ナンバーの登録条件は1ナンバーとほとんど同じですが、一部が異なります。
- 「長さ4.7m、幅1.7m、高さ2m、排気量2,000cc」以下であること
- 荷台の面積が1㎡以上あること
- 座席部分よりも荷台スペースが広いこと
- 荷台に積載した荷物の重量が乗車した人員よりも重いこと
- 座席と荷台の間に仕切りが設けられていること
中古トラック一覧
トラックの高速料金は車両区分や走行距離をチェック
トラックの車種区分には「普通車」「中型車」「大型車」「特大車」があり、それぞれ車体の寸法や車軸によって分けられます。
車種区分によって高速料金に違いが発生するほか、走行距離が伸びた場合も料金が上がっていきます。
ただし、走行距離が長くなるほど割引もされます。
現在は100〜200kmで25%、200km以上で一律30%の割引率です。
また、対象となる高速道路を、ETCを利用して0時から4時までの間に走行していれば、通行料金が30%割引になる深夜割引もあります。
どちらの割引も今後変更になる予定なので、チェックが必要です。
自分のトラックがどの車両区分に値するかは、車体の寸法、ナンバープレートの大きさ、分類番号で確認しましょう。
トラックの購入や買取をご検討中の方は、ぜひグットラックshimaへお気軽にお問い合わせください!
トラックやバスなどの販売や買取、リサイクルまでをトータルで行っています。
豊富なラインアップを用意しており、ホームページから簡単に検索できますよ!


 企業情報
企業情報