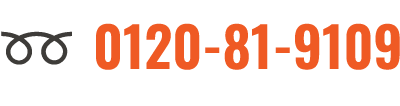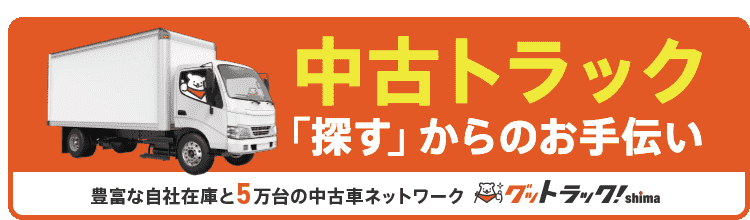2022.09.07
高所作業車の種類とは?種類ごとの特徴や乗る前の注意点を解説
こんにちは!グットラックshimaです!
電気工事や通信工事など、高い場所での作業にかかせない「高所作業車」。
高所作業車には、動力・構造・走行方式によってもさまざまな種類があります。
中でもトラック式の高所作業車は、昇降装置がトラックに搭載されているため作業効率が良く、公道の走行も可能なので移動もスムーズに行えるんですよ!
今回は、高所作業車について詳しく解説。
高所作業車の特徴や用途、種類、そして乗る前の注意点もご紹介します。
中古トラック一覧
目次
高所作業車の種類とは?動力・構造・走行方式での違いを確認!
高所作業車とは、文字通り高い場所で作業をする際に使用する建設車両です。
さまざまなタイプがありますが、高所作業車の定義は次の3点となっています。
<高所作業車の定義>
- 2m以上の高さに上昇できる作業床(作業用バスケット)を備えている
- 走行機能や昇降機能を搭載している
- 不特定の場所を自走する際や上昇・下降時に動力を使用する
以上の定義に該当する車両は高所作業車に該当しますが、動力・構造・走行方式によっても種類が異なります。
使用する用途や作業現場に応じて、ベストな1台を選びましょう。
動力装置による種類
「動力」とは、機械などを動かすために必要なエネルギーのこと。
高所作業車の動力装置には、下記の3種類があります。
エンジン式
エンジンで駆動する高所作業車を「エンジン式高所作業車」といいます。
ディーゼルエンジンが主流です。
走行時の動力だけでなく、高所作業時に使用するブームの油圧も作り出すため、効率にも優れています。
排気ガスを発生させ、騒音も伴うため、屋外での使用に適しています。
バッテリー式
バッテリーを複数搭載し、駆動する「バッテリー式高所作業車」。
複数のバッテリーがモーターを動かしたり、油圧を作り出したりするため、そこから走行時の動力や、高所作業時に使用するブームの動力が得られます。
バッテリー駆動により排気ガスの発生がなく静かなため、屋内でも安全に使用できます。
バイエナジー式
エンジンとバッテリーをどちらも搭載している「バイエナジー式高所作業車」は、近年増加傾向にあります。
ハイブリッド車と同じく、エンジンとバッテリーを必要に応じて切り替えることが可能です。
そのため、屋外ではエンジン式に、屋内ではバッテリー式に切り替えるというように、使い分けることができますよ。
昇降機構の構造による種類
高所作業車には、昇降し高さを変える装置である「昇降機構」があります。
昇降機構の構造にもさまざまな種類があるため、確認してみましょう。
<垂直昇降式>シザース式
はさみを開いたような形状の支持脚を組み合わせた、パンタグラフ方式の昇降機構を取り入れている「シザース式高所作業車」。
バスケット(作業床)を2点で支えることで高所でも揺れが少なく、垂直に昇降できます。
<垂直昇降式>マストブーム式(垂直マスト式)
作業床が垂直に昇降する構造には「マストブーム式(垂直マスト式)高所作業車」もあり、主に小型の作業車に採用されています。
マストは何段かに分けられて収納されており、油圧によって昇降できます。
機動性が高いため、スペースが限られた現場でも活躍します。
<ブーム式>直進ブーム式(伸縮ブーム型)
名前の通り、ブームがまっすぐに伸びるタイプの「直進ブーム式高所作業車」。
「伸縮ブーム型」とも呼ばれています。
作業位置へ直線的に接近が可能となっています。
ブームは何段かに分けられて収納されており、油圧によって伸縮することで昇降できます。
<ブーム式>屈折ブーム式(屈伸ブーム型)
「屈折ブーム式高所作業車」の場合、ブームの中間が屈折していることが特徴です。
ブームの伸び縮みが可能なことから「屈伸ブーム型」とも呼ばれています。
旋回機能も付いていることから狭い場所はもちろんのこと、障害物がある現場でも効率よく作業できますよ。
直進ブーム式と同じく、ブームが何段かに分けられて収納されており、油圧によって伸縮することで昇降できます。
走行方式(走行装置)による種類
走行方式(走行装置)は大きく分けて「トラック式」と「自走式」があります。
トラック式
「トラック式」とは、その名の通りトラックの荷台に高所作業機能のある機械を架装したもの。
昇降装置がトラックに搭載されているため作業効率が良く、通常のトラックと同様に一般道でも走行できるため、移動もスムーズに行えます。
トラック式高所作業車は移送するための搬送料が別途必要なく、その分のコストを削減できます。
自走式
「自走式」は走行機能を持っている重機で、ほかの動力は使用しません。
「クローラ式」「タイヤ式(ホイール式)」の2種類があります。
ちなみに、自走式高所作業車は一般道を走行できません。
移送するためのトラックやトレーラーといった移送車両が別途必要です。
クローラ式
走行部分が無限軌道(キャタピラー)となっている「クローラ式」。
不整地といった足場の悪い場所でも高所作業が可能です。
タイヤ式(ホイール式)
走行部分がタイヤとなっているため、自動車感覚で現場内を走行できる「タイヤ式(ホイール式)」。
床に走行跡を残さないノンマーキングタイヤを選べば、屋内でも使用できます。
※この他に、トラック式の公道も走れる機動性と、自走式の作業効率性を兼ね備えた「移動式高所作業車」もあります。
グットラックshimaではさまざまな中古の高所作業車を販売しています。
ぜひ在庫をチェックしてくださいね!
高所作業車に乗る前に知っておくべき注意点は2つ!

高所作業車に乗る前の注意点として、法定点検や必要な資格についてしっかり知っておきましょう。
高所作業車は、労働安全衛生法第45条により定期に自主検査を行うことが義務付けられており、特定の機械については1年以内に1回「特定自主検査(年次点検)」という法定点検を受ける必要があります。
有資格者による自主検査を行い、特定自主検査記録票に記載した検査結果は、3年間保存しなくてはいけません。
また、高所作業車を運転する際や高所での作業をする際には、労働安全衛生法で定められた資格が必要になります。
資格は高所作業車の作業床の高さによって異なります。
- 作業床高10m以上の高所作業車:「高所作業車運転技能講習」(Cコースの場合/学科試験も含めて12時間・実技6時間)を修了する必要あり
- 作業床高10m未満の高所作業車:「高所作業車特別教育」(学科6時間・実技3時間)を修了する必要あり
※トラック式高所作業車を公道で走行する場合は、運転免許証も必要です。
中古トラック一覧
高所作業車の種類は動力・構造・走行方式で異なる!用途に応じた選択を
高所作業車とは、文字通り高い場所で作業をする際に使用する建設車両のことで、定義としては次の3点があります。
- 2m以上の高さに上昇できる作業床(作業用バスケット)を備えている
- 走行機能や昇降機能を搭載している
- 不特定の場所を自走する際や上昇・下降時に動力を使用する
高所作業車は動力、昇降機構の構造、走行方式によっても、下記のようなさまざまな種類があります。
- 動力装置の種類:エンジン式、バッテリー式、バイエナジー式
- 昇降機構の構造の種類:【垂直昇降式】シザース式、マストブーム式(垂直マスト式) 【ブーム式】直進ブーム式(伸縮ブーム型)、屈折ブーム式(屈伸ブーム型)
- 走行方式(走行装置)の種類:トラック式、自走式(クローラ式、タイヤ式・ホイール式)
使用する用途や作業現場に応じてベストな高所作業車を選びましょう。
高所作業車に乗る前には、法定点検や必要な資格についても必ず確認してくださいね。
グットラックshimaでは、さまざまな中古建機を販売しています。
豊富なラインアップをホームページから簡単に検索できますよ!
お気軽にお問い合わせください。


 企業情報
企業情報