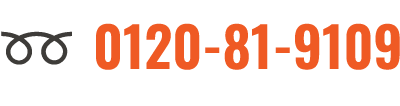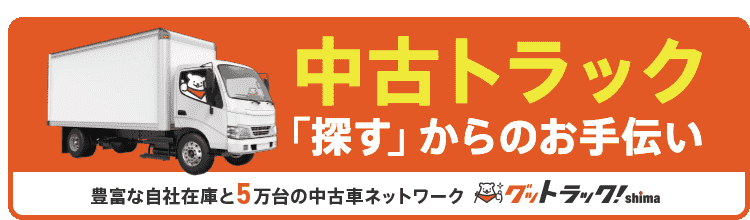2025.08.16
トラックの耐用年数は?減価償却方法や買い替えの目安も解説
こんにちは!グットラックshimaです!
トラックを会社の経費で購入し、業務用車両として使用するためには、「減価償却」という経理上の処理が欠かせません。
そしてその処理には、「耐用年数」という基準を用いて計算するのが一般的です。
では、耐用年数を用いた減価償却は、どのように行えば良いのでしょうか。
今回は、トラックの耐用年数と減価償却の方法について解説します。
耐用年数を目安としたトラック買い換えのタイミングについても触れていきますので、参考にお役立てください。
中古トラック一覧
目次
耐用年数とは?そのトラックの耐用年数、何年?
まずは、トラックの耐用年数とは何なのかご説明します。
耐用年数とは
一般的に、短期間で消費してしまうコピー用紙やボールペンといった「消耗品」と比較すると、トラックなどの車両やパソコンなどの電子機器は、複数年に渡って使用することが可能です。
しかし、永久に使えるものでもなく、いずれ使用できない時期が来ます。
このように複数年にわたって使用できる備品・設備を「耐久消費財」と呼びます。
年々価値が目減りしていく「耐久消費財」は、経理上、購入したときに一括計上することはなく、使用年数で分割した金額を、年度ごとに計上するのが決まりとなっています。
とはいえ、実際のところ、備品や設備が使えなくなるタイミングはケースバイケースで、誰にもわかりません。
その備品・設備がいつまで使えるかわからないまま、1年ごとに分割して費用を計上するのは困難です。
この問題を解決するため、会計処理にあたっては、一般的な各備品・設備の寿命をもとに、「Aという備品・設備なら何年間は使用することができる。対象年数の間は経費を分割して計上する」ことが法律で定められています。
この年数が、「耐用年数」です。
例えば、パソコンであれば耐用年数は4年、普通自動車の社用車であれば耐用年数は6年となります。
トラック(新車)の耐用年数
新車トラックの法定耐用年数は、条件によって以下のように決められています。
【自家用トラック(貨物自動車)】
- ダンプ式のもの:4年
- ダンプ式以外のもの:5年
【事業用トラック(運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具)】
- 大型乗用車(総排気量が3リットル以上):5年
- 小型車(積載量が2トン以下):3年
- その他の自動車:4年
- 被けん引車、その他:4年
【特殊自動車(トラックミキサーやレッカーなどの特殊車体)】
- 小型車(総排気量が2リットル以下):3年
- その他のもの:4年
トラックの耐用年数は、「自家用か事業用か」という用途と「車両の形状・性能」によって異なります。
上記の耐用年数は単純にトラックの寿命というわけではなく、経理上の処理として減価償却可能な期間を指します。
実際のトラックの使用可能期間とは異なり、帳簿上の価値がゼロになった後も、車両自体が問題なく稼働していれば引き続き使用することが可能です。
中古トラックの耐用年数
では、中古で購入したトラックの場合、トラックの耐用年数はどのように確認すれば良いのでしょうか。
中古トラックの耐用年数は、「簡便法」という方法で算出します。
その計算式は、以下のとおりです。
【法定耐用年数が残っている場合】
- 法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2
【法定耐用年数が残っていない場合】
- 法定耐用年数×0.2
※小数点以下は切り捨て
※算出した年数が2年未満の場合は一律2年とする
法定耐用年数がまだ残っている中古トラックについては、法定耐用年数から経過した年数を引き、そこに経過年数の20%を足したものが、現状の耐用年数となります。
一方、法定耐用年数を経過してしまっている中古トラックについては、法定耐用年数の20%を現状の耐用年数とします。
中古トラックの耐用年数計算例
前述した簡便法による中古トラックの耐用年数の計算例をご紹介します。
【法定耐用年数が残っている場合】
例)法定耐用年数4年、経過年数1年の中古トラックの場合
4年-1年+1年×0.2=3.2年※小数点以下切り捨て
→耐用年数は3年
【法定耐用年数が残っていない場合】
例2)法定耐用年数5年、経過年数6年の中古トラックの場合
5年×0.2=1年※算出した年数が2年未満の場合は一律2年とする
→耐用年数は2年
トラックにおける減価償却の仕方は?
ここからは、耐用年数を用いて行うトラックの減価償却について解説していきます。
減価償却とは、会計処理において備品や設備の費用を、それぞれの耐用年数に応じて、毎年分割して計上することを「減価償却」と呼びます。
備品・設備の価値は年々下がっていくため、そのときどきの資産価値を会計処理に反映させることが、減価償却の目的です。
減価償却の対象となるのは、使用可能期間が1年以上かつ取得金額が10万円以上の固定資産に限られます。
減価償却の方法は「定額法」と「定率法」の2種類
減価償却の計算方法には、以下の2種類があります。
- 定額法
- 定率法
資産の内容によっては定額法しか選べないものもありますが、トラックのような車両は、各法人・事業主の方針によって選択することが可能です。
なお、平成24年4月1日以降に取得した資産については、原則として「定額法」が適用されるため、特段の選択をしていなければ定額法で処理されていることが多いです。
また、減価償却できる費用には、車両本体価格だけでなく車両取得に直結する手数料や消費税なども含まれます。
定額法や定率法を用いた減価償却の計算方法では、耐用年数を用います。
中古トラックの場合、耐用年数は前述した方法で計算し直す必要があるので、注意しましょう。
定額法による減価償却
定額法は、「車両の取得価額」に規定の「償却率」を乗じて計算する方法です。
このとき使う償却率は、耐用年数に応じて決められています。
償却率の一覧は、国税庁「減価償却資産の償却率等表」をご確認ください。
定額法では、上記の式で算出した金額を、耐用年数のある期間中(償却期間)、毎年計上することになります。
例)5年の耐用年数となる100万円の車両を購入した場合
100万円×0.2(償却率)=20万円
→20万円を5年間毎年計上する
(※資産の現存を証明するため、最終年度はマイナス1円した額を計上)
毎年の評価価値が一定となり、計上処理がしやすい点が、定額法の特徴です。
定率法による減価償却
定率法は、未償却の残高に対し一定の率を乗じた金額を、毎年減価償却していく方法です。
毎年同じ金額を計上する定額法と異なり、価値が一番高い時期に一番多く経費計上し、その後の計上金額は下がっていくことになります。
先に多めに税金を払っておくことで、将来的な買い替えどきの負担が軽くなることから、定率法を採用する法人は多くなっています。
定率法では、1年目は定額法と同じく、「車両の取得価額」に償却率を乗じて償却費を算出します。
ただし2年目以降は、「車両の取得価格」から「すでに経費計上した分(既補償額)」を差し引き、そこに「償却率」を掛けた額を計上します。
定率法の償却率は、定額法の2倍となります。
ただし、定率法では対象期間ずっと同じ償却率で計上していくと、マイナスになってしまう場合があります。
これを避けるために「保証率」というものもあらかじめ決められています。
その年の元となる資産価値(償却補償額)が、「車両の取得金額」に「保証率」を乗じて割り出された金額(償却補償額)を下回った場合には、計算方法を定額法へ変更します。
変更後の定額法での計算には、改訂償却率を用います。
定率法の償却率や保証率、改訂償却率については、国税庁「減価償却資産の償却率等表」でもご確認ください。
例)5年の耐用年数となる100万円の車両を購入した場合
- 償却率:0.4(定額法償却率0.2の2倍)
- 保証率:0.108
- 改定償却率:0.5
- 償却補償額:1,000,000×0.108=108,000
1年目:1,000,000×0.4=400,000円
2年目:(1,000,000-400,000)×0.4=240,000
3年目:(1,000,000-640,000)×0.4=144,000
4年目:(1,000,000-784,000)×0.4=86,400
4年目の答えが償却補償額(108,000円)を下回ったので、定額法(改訂償却率を適用)に切り替え
4年目:(1,000,000-784,000)×0.5=108,000
5年目:((1,000,000-784,000)×0.5)-1=107,999 ※残高は1円に
途中で計算方法や使用する率が変わる点が、定率法の注意点です。
トラックに長く乗るためには?車両の寿命を延ばす秘訣

耐用年数に関わらず、トラックを長持ちさせるには、日常的に以下のポイントに気をつけることが大切です。
ポイント1:こまめなメンテナンス
トラックの寿命を延ばすために、こまめなメンテナンスは欠かせません。
ひと手間かけてあげることで、寿命は格段に延びやすくなります。
●●キロ走行ごと・毎月●●日にメンテナンスをする、という決まりを会社で設けておくとメンテナンスの習慣は身に付きやすいでしょう。
具体的なメンテナンスの内容としては、以下のようなものが挙げられます。
エンジンオイルの定期交換
長距離を走る可能性の高いトラックでは、短期間でオイルが汚れてしまうことがあります。
小型トラックで2万km、大型トラックで4万km走行を目安に、オイルの交換を行いましょう。
また、短距離~中距離の走行が中心である場合も、定期点検時には必ずチェックしましょう。
傷の補修やサビの管理
車両の傷や穴は、そのままにしておくとサビの原因となり、車両の寿命を縮めます。
傷や穴に気が付いたら速やかに補修するとともに、サビの元となる汚れや水分はきちんと落とすことが大切です。
また、寒い地域では融雪剤もサビにつながりやすいので注意しましょう。
タイヤの適切な交換
古いタイヤを使い続けていると、車体に負担をかけるだけでなく安全面でも危険が生じます。
タイヤそのものの定期点検と交換も忘れずに。
ポイント2:負荷をかけない運転
トラックの寿命を長持ちさせるためには、なるべく車両に負荷をかけないよう気をつけることも大切です。
具体的には、以下のような点を意識しましょう。
丁寧で余裕のある運転
急ブレーキや急発進など、急な動きを要する運転は、トラックの車体に大きな負荷をかけてしまいます。
安全のためにも、運転は丁寧に行うことが重要です。
適切な暖機運転
冬期間寒い地域で運転する場合は特に、全く準備運動をさせないまま運転を開始すると、車体に大きな負担がかかります。
逆に、暖機運転が長すぎるのも車体や環境に良くありません。
車体の負担を軽減させるためには、エンジンをかけて数分でゆっくり走行をはじめ、ウォームアップ走行すると良いでしょう。
また、夏はエンジンを掛けたらエアコン待ちせずスタートするのが理想です。
過積載に注意
荷物の積み過ぎは、車体に大きな負担を与えます。
規定の積載量に対し、実際の積載量には十分余裕をもっておきましょう。
トラックの買い替えは耐用年数以外でどこを見て判断する?

大切にトラックに乗っていても、いつかは買い替えの時期が来ます。
一般的にはどんなタイミングで買い替え時期を設定しているのでしょうか?
ここでは、そのタイミングについて解説します。
車両の用途や積載物の規格が変わったとき
やむを得ない買い替えの一つに、車両の用途や積載物の規格が変わったときがあります。
特に使っている資材・備品の変更があって今までの車両では業務が難しい場合、まだ使える車を手離すことは珍しくありません。
減価償却が満了したとき
ご紹介した減価償却が満了となったときも、トラックの買い替えを考えるタイミングの一つ。
減価償却が終われば、車両の資産価値に関する課税もなくなるので、費用を捻出しやすくなります。
修理代が高額になったとき
車両が故障し、その修理代が高額になったときも、トラックの買い替えを検討するタイミングです。
その修理代が車両を買い替える費用より高くなるなら、手放して新しい車両を購入しようと考える方は多いでしょう。
車両の年式が古くなったとき
年式が古くなってくると、トラックの燃費は悪化し、必要な運用コストはどうしても嵩みます。
車の部品が手に入らなくなることもあるでしょう。
あらゆるリスクやデメリットを抑えるためにも、車両の年式が古くなってきたときには、車両の買い替えを検討する必要があります。
走行距離の目安を超過したとき
トラックをはじめとした車には、走行距離の寿命の目安もあります。
トラックの場合、その目安は以下のとおりです。
小型トラック
小型トラックは以下の条件のトラックを指し、走行距離の目安は約20万kmとなります。
- 車両総重量:5トン未満
- 最大積載量:3トン未満
- 特徴:コンパクトで、地場輸送や近距離の配送、山間部などでの走行に適しています
※2tトラックと呼ばれるものも小型トラックに含まれます
中型トラック
中型トラックは以下の条件のトラックを指し、走行距離の目安は約40〜50万kmとなります。
- 車両総重量:5トン以上11トン未満
- 最大積載量:3トン以上6.5トン未満
- 特徴:近距離から中距離の輸送に適しており、引越しや食品輸送など幅広い用途で利用されます
※4tトラックと呼ばれるものも中型トラックに含まれます
大型トラック
大型トラックは以下の条件のトラックを指し、走行距離の目安は約70万kmとなります。
- 車両総重量:11トン以上
- 最大積載量:6.5トン以上
- 特徴:幹線輸送や長距離輸送など、大量の荷物を一度に運ぶのに適しています
※10tトラックと呼ばれるものも大型トラックに含まれます
車両の状態にもよりますが、上記の目安を超過したとき・超過する前も、買い替えを検討すべきタイミングです。
トラックの走行距離の目安については、「中古トラックの走行距離と寿命の関係は?買い替えの目安も」でより詳しく解説しています。
買取価格とのバランスが良いとき
車両の寿命はきていなくとも、買取価格が高いうちに売却を考えるという方もいるでしょう。
買取価格が高いタイミングで買い替えることで、次に買う車両の元手を多く確保することができます。
耐用年数などで買い替えを考える場合は新車と中古車どっち?
買い替えをする時には、新車を購入するか・中古車を購入するかで迷う方もいるでしょう。
ここでは、新車・中古車の判断のポイントを確認していきます。
新車の購入が向いている場合
新車の購入は、以下のような希望がある方に向いています。
- 車両の資産価値を保ちたい
- 資金に比較的余裕がある
- 新車のほうが安心感がある
新車は中古車に比べ金額が高いですが、その分資産価値も上がります。
数年程度での買い替えを考えているのであれば、高額での買取も期待できるでしょう。
また、やはり新車のほうが安心だ・中古車は故障が心配だと感じる方にも、新車の購入が向いています。
中古車の購入が向いている場合
中古車の購入は、以下のような希望がある方に向いています。
- 車両を乗り潰す予定である
- 資金を抑えたい
- 車両台数を揃える必要がある
将来的な買取を期待せず、購入時の資金をなるべく抑えたいという場合に、中古車の購入は向いています。
また、車両台数を揃えなくてはならない場合、新車では費用がかなりかさみますが、中古車であれば、比較的用意がしやすくなります。
中古トラックの購入の流れについては、「中古トラック購入の流れとは?必要書類や注意点もご紹介!」をチェックしてみてくださいね。
買い替えのタイミングが来ても理想の車両が見つからない場合や、期間限定で台数を増やしたいという場合などには、リース契約を視野に入れるのも良いでしょう。
中古トラック一覧
トラックの耐用年数と減価償却の知識は必須!メンテナンスも大切
トラックを会社の備品として使用するためには、会計処理上の減価償却と耐用年数の知識が欠かせません。
正しく経費として計上すれば節税にもつながりますので、正しく理解し、しっかり処理を行いましょう。
また、きちんとメンテナンスを行えば、車は耐用年数を越えても安全に使えます。
会社でメンテナンスを行うタイミングを定めておけば、メンテナンスの習慣が付きやすいので安心ですね。
そして、車両の買い替えのタイミングには減価償却が一つのきっかけとなることも。
迷ったら選択肢の一つにリース契約を入れるのも良いでしょう。
トラックの買取や購入は、グットラックshimaへおまかせください!
リース契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。


 企業情報
企業情報